2023年9月12日のApple新製品発表会で披露されたiPhone 15シリーズ。その最大のトピックのひとつは、2012年のiPhone 5以来、10年以上iPhoneの象徴であり続けた独自規格の充電・データ転送ポート「Lightning(ライトニング)」の廃止と、業界標準である「USB Type-C(以下、USB-C)」への完全移行でした。

この変更は当然ながら世界中の何億人ものiPhoneユーザーに直接的な影響を与えました。長年買い溜めてきたLightningケーブルや、イヤホン、充電ドック、外部マイクといった数多くの対応アクセサリが、新しいiPhoneでは直接使えなくなるためです。
「なぜ今さら変えるのか?」「USB-Cはそんなに優れているのか?」「また新しいケーブルを買わなければいけないのか?」といった素朴な疑問が、多くの人々の心に浮かんだはずです。
結局、なぜiPhoneのLightning規格はUSB-Cに「敗れた」のでしょうか。その技術や規制の裏側を見ていきましょう。
「独自規格」vs「業界標準」LightningとUSB-Cのそもそもの違い

両者の最も根本的な違いは、その「生まれ」にあります。
Lightningは、Appleが自社製品のためだけに開発した「独自規格(プロプライエタリ規格)」です。2012年に登場して以来、iPhone、iPad(一部モデルを除く)、AirPodsの充電ケースなど、Appleのエコシステム内でのみ使用されてきました。これは、ユーザー体験の品質を自社で完全にコントロールし、サードパーティ製アクセサリの品質を管理するというAppleの方針でした。一方でLightningはApple製品以外との互換性は一切なく、極めて閉鎖的な規格であったと言えます。
一方、USB-Cは、USB Implementers Forum (USB-IF) という業界団体によって標準化された「オープンな業界標準」です。Appleだけでなく、Samsung、Google、SONYといったAndroidスマートフォンメーカー、DellやHPといったPCメーカーまであらゆる企業が自社製品に採用しています。
・閉鎖的な規格
・オープンかつ業界標準の規格
この両者を比較した際に、メーカーやサードパーティーの事業者、そして何よりもユーザーがどちらの規格を求めるかは一目瞭然でしょう。AppleがUSB-Cへの移行を最終的に決めたのも、ある意味で当然だったと言えます。
問題は、USB-Cという技術的に優れた業界標準規格が存在するにもかかわらず、なぜAppleは10年以上も独自規格に固執し続けたのか、そして、なぜ今になってその方針を転換したのか、という点にあります。
性能差について
なお、USB-CとLightning規格には性能差もあります。USB-Cは、充電速度とデータ転送速度の両面でLightningよりも優れています。
たとえばLightningケーブルは、USB 2.0規格に基づいており、最大480Mbpsのデータ転送速度です。一方でUSB-Cは、USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2など、より高速な規格に対応しています。たとえば、USB 3.2 Gen 2であれば、最大10Gbpsの転送速度を実現できます。
やはりこうした点からもUSB-CのLightningに対する優位性は明らかです。
Appleを動かした、EU「共通充電器」規制
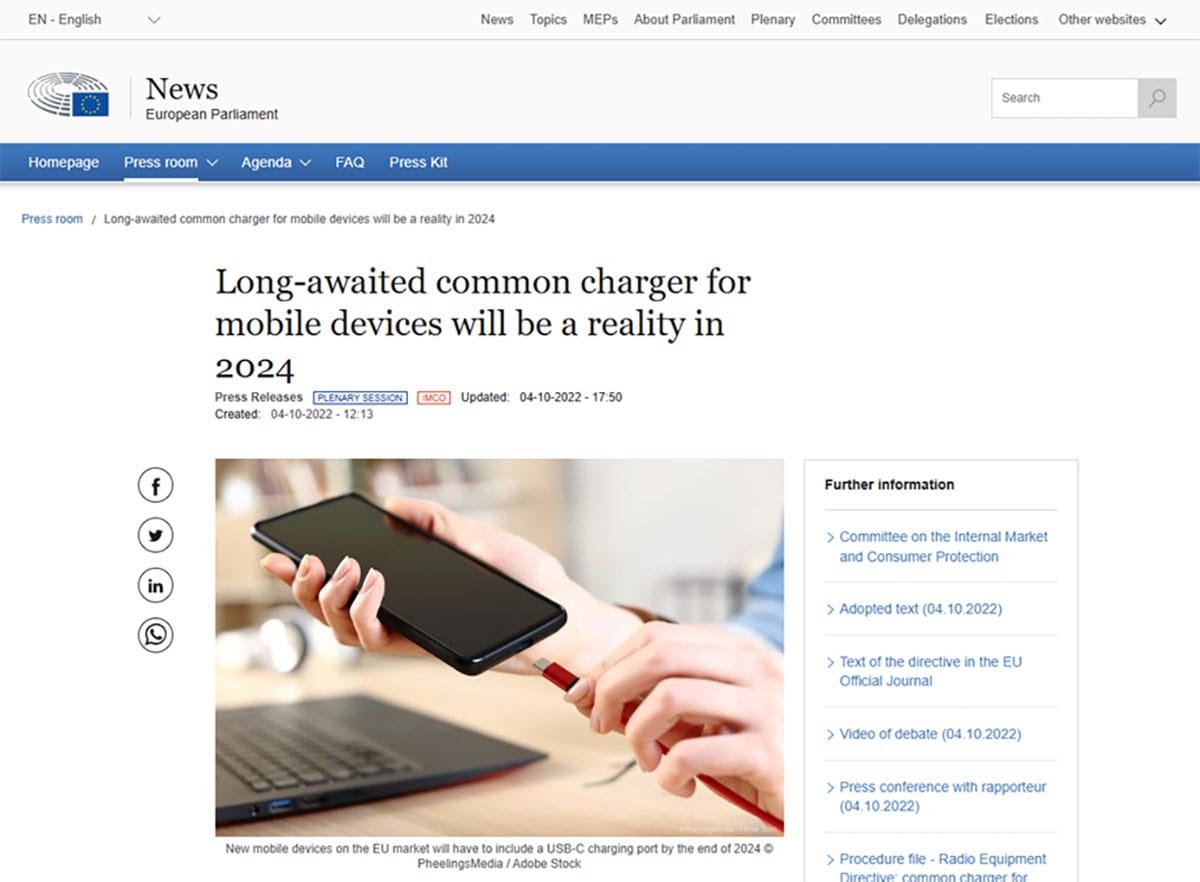
技術仕様上、USB-CはLightningより高速な転送速度などで優位性を持っています。しかし、Appleが長年かけて築いてきた独自のエコシステムを手放したのは自らの判断ではありませんでした。実際、USB-C採用の裏にあったのは技術的な合理性やユーザーの利便性ではなく、「外的圧力」。それが、EU(欧州連合)が導入した「共通充電器(Common Charger)」に関する規制です。
この規制はEU域内での充電器統一に向けた取り組みの結果、EUの立法機関が2022年10月に「無線機器指令(Radio Equipment Directive)」の改正案として圧倒的多数で可決したもの。通称「共通充電器指令」と呼ばれる法律です。
簡単に言うと、この法律は「2024年12月28日までに、EU域内で販売されるすべてのスマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ヘッドホン、携帯型ゲーム機などの特定の電子機器について、有線充電ポートをUSB-Cに統一することを義務付ける」という内容です。
さらに、この規制は2026年春からはノートPCにも適用範囲が拡大されることが定められています。 この法律は特定の企業名を挙げてはいませんが、事実上、市場で唯一USB-C以外の独自ポート(Lightning)を主要スマートフォンに採用し続けていたAppleをターゲットにしたものであることは、誰の目にも明らかでした。
このEUの決定は、Appleに極めて重い経営判断を迫るものでした。選択肢は、事実上二つしかありません。
・EU市場でのiPhone販売を継続するために、Lightningを諦めてUSB-Cに移行する。
・Lightningに固執し、世界最大級の経済圏であるEU市場から撤退する。
言うまでもなく、後者は現実的な選択肢ではありません。AppleにとってEUは、北米、中国と並ぶ最重要市場のひとつです。この巨大市場を失うことは、ビジネス上、到底受け入れられるものではありませんでした。したがって、Appleに残された道は、実質的に「USB-Cへの移行」一択だったのです。
そもそもなぜAppleはLightningに固執し続けたのか?
最終的にAppleは、EUからの強い外圧に抗しきれず、Lightning規格からUSB-Cへの移行を決断したと言えるでしょう。しかし、Appleが「ぎりぎりまでUSB-Cへの移行に抵抗した」背景には、「MFi(Made for iPhone/iPad/iPod)認証プログラム」の存在が大きく関係しています。
この制度は、Apple以外のメーカー(サードパーティ)がLightning端子を搭載したアクセサリを製造・販売する際に、Appleのライセンス認証を受けることを義務付けるものです。
メーカーは、Appleの定めた品質基準を満たし、ライセンス料を支払うことで、製品にMFi認証のロゴを表示することができます。さらに、ケーブルやアクセサリにはApple独自の認証チップを組み込む必要がありました。Appleは、このライセンス料やチップの販売を通じて、莫大な利益を得ていたとされています。
MFiプログラムは、Appleにとって二重のメリットがありました。ひとつは、粗悪なアクセサリによる故障や事故を防ぎ、ユーザー体験の質を保つこと。もうひとつは、「Lightningエコシステム」と呼ばれる閉鎖的な市場を自社で支配し、安定した収益を確保できる点です。USB-Cというオープンな規格を採用することは、Appleにとって利益率の高いこの「黄金の城」を自ら手放すことを意味していました。
AppleはEUの規制要求に対応するため、Lightning規格からUSB-Cへの移行を決断したと言えます。しかし「ぎりぎりまでUSB-Cへの移行に反発した」要因としては、「MFi(Made for iPhone/iPad/iPod)認証プログラム」の存在が挙げられるでしょう。これは、サードパーティ(Apple以外のメーカー)がLightning端子を搭載したアクセサリを製造・販売する際に、Appleからライセンス認証を受けることを義務付ける制度です。
メーカーは、Appleが定めた品質基準を満たし、ライセンス料を支払うことで、製品にMFi認証ロゴを表示できます。そして何より、ケーブルやアクセサリに特殊な認証チップを組み込む必要がありました。Appleはこのライセンス料と認証チップの販売から、莫大な利益を得ていたとされています。
このMFiプログラムは、Appleにとって二重のメリットがありました。ひとつは、粗悪なアクセサリによるデバイスの故障や事故を防ぎ、ユーザー体験の品質を維持すること。そしてもうひとつが、この「Lightningエコシステム」という閉鎖的な市場を支配し、安定した収益源を確保することです。USB-Cというオープンな規格を採用することは、この収益性の高いビジネスモデルを自ら手放すことを意味したのです。
ブランド戦略との兼ね合いも大きい
もうひとつの理由は、Apple製品ならではの「シームレスな体験」を自社の管理下に置きたいという、同社の思想です。ハードウェアからソフトウェア、そして周辺アクセサリに至るまで、すべてを自社でコントロールすることで、最高のユーザー体験を提供する。これがAppleのブランド戦略の核です。独自規格であるLightningは、まさにその思想を体現するものでした。どのケーブルを使っても、どのアクセサリをつないでも、Appleが意図した通りの性能と品質が保証される。この徹底した管理体制こそが、多くのユーザーを惹きつける「Appleらしさ」の源泉でもありました。
USB-Cに移行するということは、このコントロールの一部を手放すことを意味します。市場には玉石混交のUSB-Cケーブルやアクセサリが溢れており、中には品質の低い製品も存在します。そうした製品を使ったユーザーが「iPhoneの充電が遅い」「データ転送が不安定だ」と感じた場合、その不満はケーブルメーカーではなく、Apple自身に向けられる可能性があります。こうしたリスクを、Appleは極度に嫌っていたのです。
しかし、最終的にUSB-Cへ移行したことで、Lightningは幕を閉じた形となりました。
次の戦いはワイヤレスか?
USB-Cへの統一で、充電規格をめぐる戦いは終わったのでしょうか。おそらく、答えは「ノー」です。Appleが究極的に目指しているのは、すべてのポートを廃した「ポートレスiPhone」ではないかという見方が近年強まっているためです。
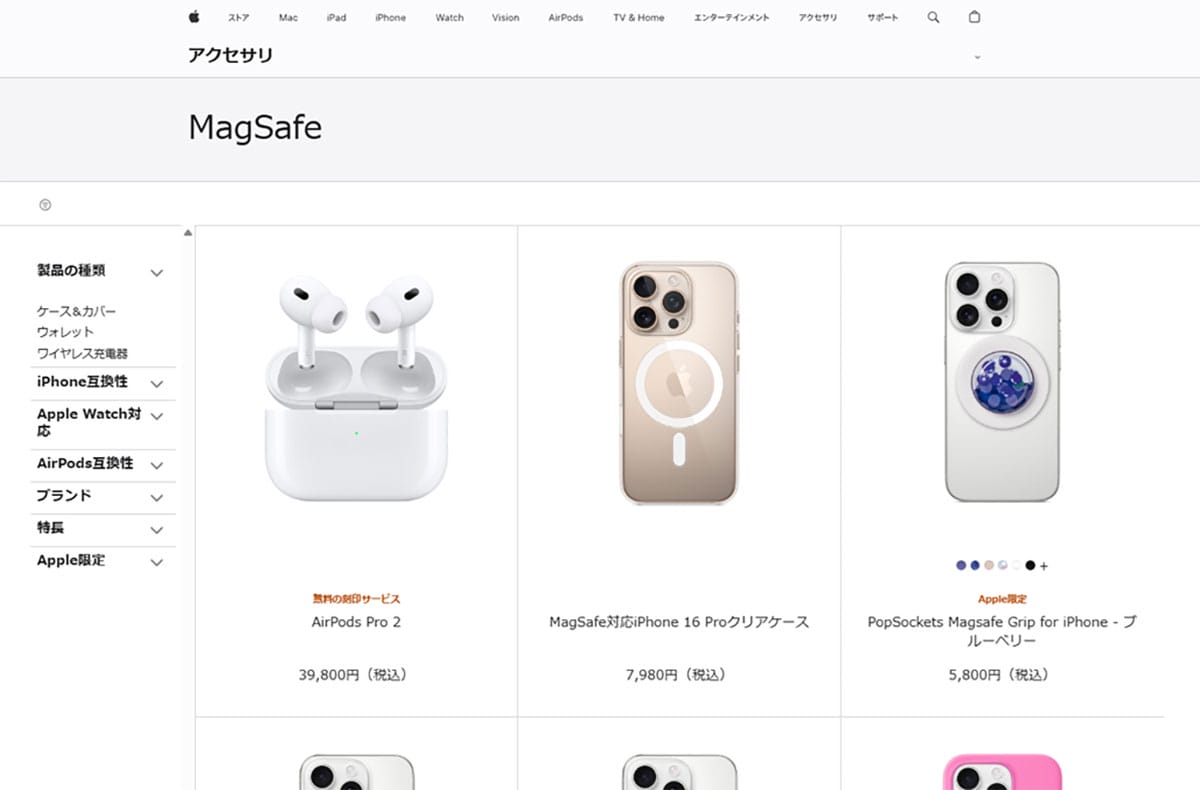
有線接続が完全になくなれば、EUの「有線充電ポート」に関する規制の対象外となります。そして、そのとき主役となるのがワイヤレス充電です。現在、ワイヤレス充電には「Qi(チー)」という業界標準規格がありますが、Appleはすでに「MagSafe」と呼ばれる独自のマグネット式ワイヤレス充電技術を強力に推し進めています。
将来的に、AppleがiPhoneからすべてのポートを排除し、充電もデータ転送も完全にワイヤレス化する日が訪れるかもしれません。そのとき、Appleは「MagSafe」を軸に新たな認証プログラムを導入し、かつてのLightningエコシステムのような、新しい形での「囲い込み」を再構築しようとする可能性があります。
Lightningをめぐる物語は、USB-Cの採用によってひとつの区切りを迎えました。しかし、それは同時に、ワイヤレスという新たな舞台で展開されるであろう次なる標準化戦争の幕開けでもあるのかもしれません。私たち消費者は、この大きな技術と戦略の変化を、これからも注意深く見守っていく必要があるでしょう。
※サムネイル画像(Image:alexgo.photography / Shutterstock.com)






