2025年9月にAppleから発売された「iPhone Air」。その薄さと軽さで、発表時にはAppleユーザーの間でから大きな注目を集めました。

しかし、発売から約1カ月が経過した現在、販売状況は厳しさを増しています。生産は大幅に削減され、一部では「ほぼ生産終了レベル」と伝えられています。同時に発売されたiPhone 17シリーズの標準モデルやProモデルは堅調な売れ行きを見せており、iPhone Airの不振は際立っています。
グローバルに対して中国市場への投入が遅れたため、同製品が中国市場で熱狂的に受け入れられる可能性も残されてはいるものの、先行きは楽観できるものではありません。
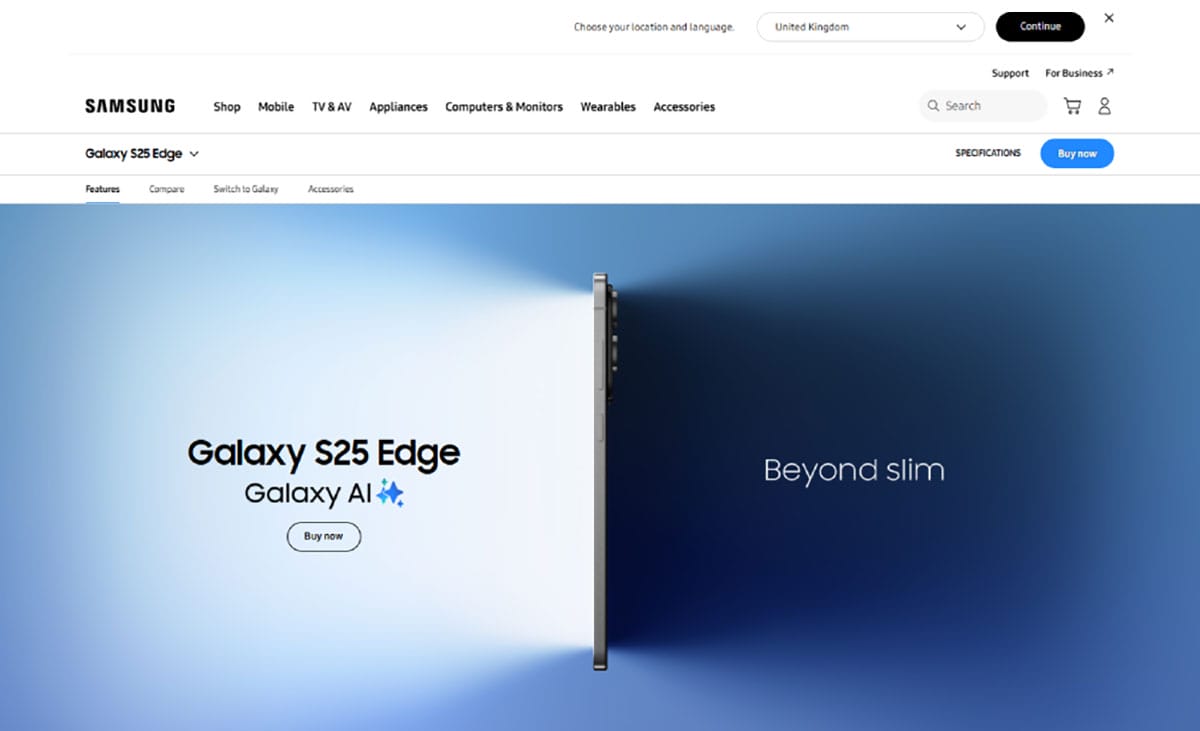
この現象はAppleに限ったことではありません。スマートフォン市場のもう一方の雄であるSamsungも、先行して投入した薄型モデル「Galaxy S25 Edge」の販売不振を受け、後継機「Galaxy S26 Edge」の開発中止を決定しました。
なぜ、技術の粋を集めたはずの「超薄型スマートフォン」は、消費者の心を掴むことができないのでしょうか。
iPhone Airと薄型モデルの現在地
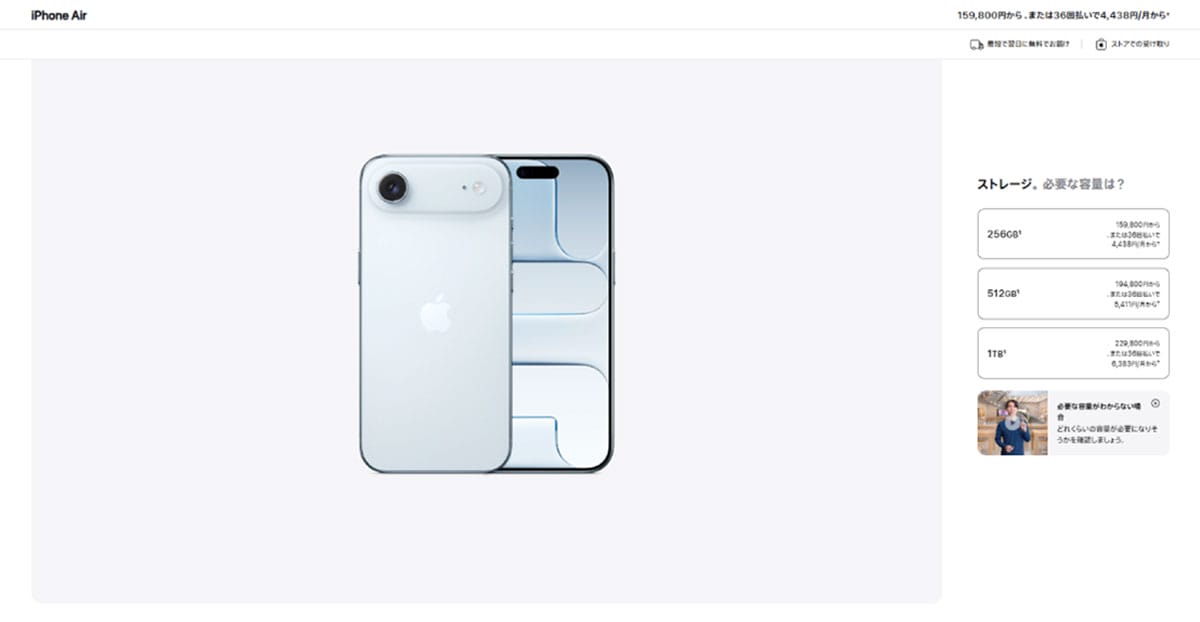
iPhone Airの販売不振は、複数の報道や調査によって明らかになっています。
人気モデルであれば予約開始から数分で配送予定日が数週間先に延びるのが通例ですが、iPhone Airは発売直後から一貫して即日配送が可能な状態が続いており、需要は限定的と言えるでしょう。一部調査では「iPhone Airの需要は事実上存在しない」とまで結論づけているケースが見受けられるほどです。
そしてNikkei Asiaは、Appleが11月以降の生産数を9月比で10%程度まで削減する計画だと報じています。また、部品サプライヤー関係者は「予測台数はほぼ生産終了モードに入った」と語り、その深刻さがうかがえます。
この不振は、iPhone 17シリーズ全体の好調さと対照的と言えます。
特に標準モデルのiPhone 17は、前モデルを大きく上回る成功を収めており、AppleはiPhone Airの減産分を他のモデルの増産に振り向けることで対応しています。結果として、シリーズ全体の生産予測は引き上げられ、Appleの収益への影響は限定的と見られていますが、「Air」という新たなカテゴリの先行きには暗雲が立ち込めています。
なお、Appleとほぼ時を同じくして、Samsungも薄型モデル市場からの撤退を決定しました。 iPhone Airに先駆けて登場した「Galaxy S25 Edge」は、その販売台数が振るわず、後継機と目されていた「Galaxy S26 Edge」の開発が中止されたと報じられています。
スマートフォン市場を牽引する2大メーカーが、ほぼ同時に「超薄型」というカテゴリで苦戦し、事実上の撤退や大幅な戦略縮小を余儀なくされたことは、市場が「薄さ」という価値を現時点では最優先事項として受け入れていない、という明確な答えを示したと言えるでしょう。
なぜ消費者は「超薄型」を選ばないのか?
「持ち運びやすい」というイメージのある「超薄型スマホ」ですが、なぜ消費者から選ばれないのでしょうか。その理由を詳しく見ていきましょう。
体験価値のジレンマ

超薄型モデルの最大の魅力は、スペックシートには現れない「感性的な価値」にあります。驚くほどの薄さ、手にした時の軽やかさ、ポケットに入れた時のかさばらなさ。一部のガジェット愛好家やYouTuberがiPhone Airを絶賛しているのは、まさにこの点を評価してのことでしょう。
しかし、この「体験しないとわからない魅力」こそが、販売においては最大のジレンマとなります。 ほとんどの人は、Apple Storeの店頭や家電量販店などに足を運んで実際に端末を操作するわけではなく「ニュース」「SNSの投稿」「YouTuberが撮影した動画」などを見て、その端末は自分にとって必要かどうかを一時的に判断します。
そして「薄さ」はすでに生活インフラと化したスマホにとって、もはや必須機能ではありません。いまや、スマホを選ぶ判断基準はバッテリー容量やカメラの数など、数値で比較できる要素に移っています。バッテリー容量やカメラの数は、まさに超薄型モデルが薄さの代わりに、典型的に犠牲にする部分でもあります。
「持つ喜び」や「所有する満足感」といった感性的な価値は、決して小さなものではありません。しかしそれが、数十万円という高価な買い物において、実用的なスペックの不利を覆すほどの決定打になるかというと、現時点では多くの人にとって「ノー」というのが市場の答えなのです。
バッテリー、耐久性、機能という「安心感」の欠如
超薄型モデルは、その設計思想上、物理的に搭載できるバッテリー容量に制約を受けます。iPhone AirやGalaxy S25 Edgeが敬遠された主な要因として、標準モデルやProモデルに比べてバッテリー容量が小さい点が挙げられます。
「薄くて格好いいけれど、夕方にはバッテリー切れの心配をしなければならない」というスマートフォンは、多くのユーザーにとって選択肢になり得ません。
さらに、「薄さ」は「壊れやすさ」という不安を想起させます。かつて「iPhone 6」で発生した、本体が曲がりやすいとされた「ベンドゲート問題」を覚えているユーザーも少なくありません。 大画面化が進む中で極端な薄さを追求することは、物理的な堅牢性への懸念に繋がり、日常的な利用でも扱いに気を使うデバイスという印象を与えてしまいます。
加えて、薄型化の代償として、カメラ性能が制限されることもあります。日常的に写真を撮影し、SNSで共有することが当たり前になった現代において、カメラ性能の妥協は大きなデメリットと受け取られます。
消費者は、「薄さ」という新たな体験価値よりも、バッテリー、耐久性、カメラといった、すでに慣れ親しんだ機能が損なわれない「安心感」を無意識に優先しているのです。
総じて現代の消費者がスマートフォンに求める本質は、より長く、より安心して、より多機能に使えるという、極めて実用的な「道具」としての信頼性にあります。
超薄型スマートフォンというカテゴリがこのまま消えていくのか、あるいはバッテリー技術の飛躍的な進化や、折りたたみスマートフォンとの融合といった新たな形で再評価される日が来るのか、現時点では誰にもわかりません。
確かなのは、スマホが多くのユーザーにとって、もはや手放せないライフラインとなっている点です。その天秤の上で、「薄さ」という魅力が「安心感」という重みを超えるには、まだ時間が必要なのかもしれません。
※サムネイル画像(Image:Hadrian / Shutterstock.com)




