社会問題化している「歩きスマホ」や「ながらスマホ」。たとえば2024年9月には横浜市でスマホを操作していた男性が踏切内で電車にはねられて死亡する事故が発生しています。防犯カメラの映像には、男性が遮断機前で立ち止まる様子が映されており、男性がスマホを操作していたために、立ち止まる場所を誤ったとみられています。
このように悲惨な事故にもつながりかねない「歩きスマホ」「ながらスマホ」ですが、実際罰則はあるのでしょうか。
「歩きスマホ」には罰則がある?

まず歩きスマホが原因で誰かにぶつかって怪我をさせたり、死亡させてしまった場合、歩きスマホをしていた側(※加害者に相当します)は、損害賠償責任を負う可能性があります。一方、「歩きスマホ」そのものに関する法的な規制はなく、各自治体の条例でも「歩きスマホ規制」にとどまり、罰則はありません。
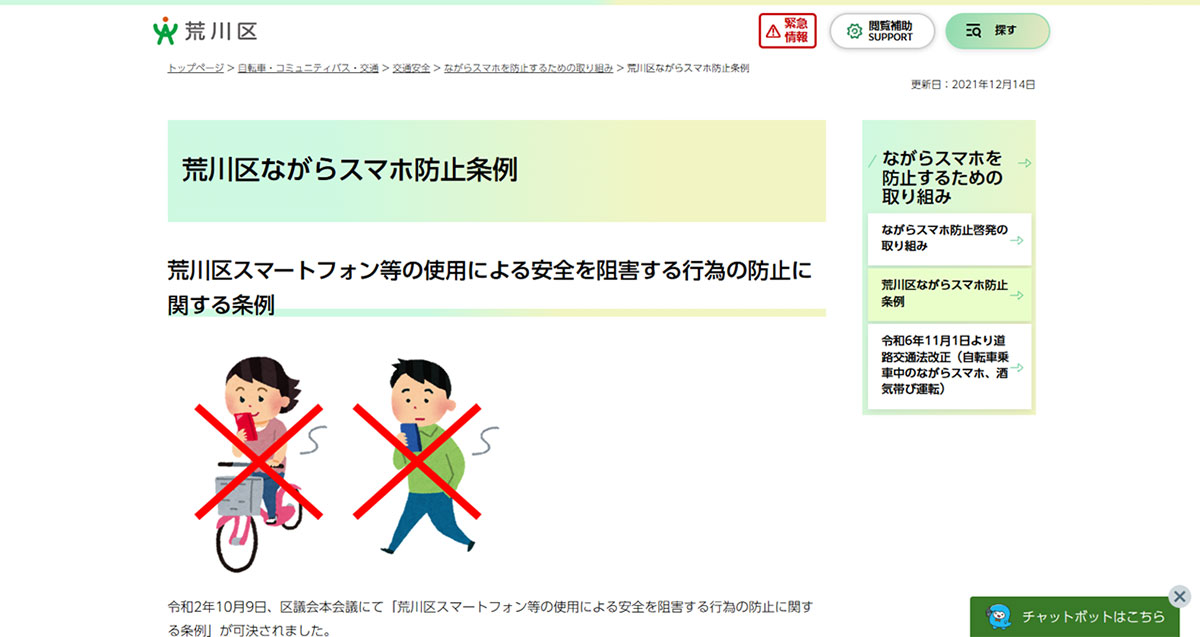
たとえば荒川区の「荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例」では、道路、公園、駅前広場、区が管理する屋外駐車場、屋外の公共の場所で「歩行中にスマートフォンやゲーム機等の画面を注視すること」が禁止されており、歩行者がスマホを使用する場合は他の通行者の妨げにならない場所で立ち止まって行わなければなりません。
しかし、条例違反をした場合の罰則はなく、啓発活動や注意喚起が主な対応となっていると言えるでしょう。同様にそのほかの自治体でも公共の場所での歩きスマホを禁止するケースが増えてきていますが、具体的な罰則そのものは定めていないことが多いです。
「ながらスマホ」には罰則がある?
「ながらスマホ」の場合、歩きスマホとは違って自転車や自動車に乗っていることになるため、罰則が存在します。
自転車の場合
自転車運転中のスマホ操作は2024年11月の道路交通法改正によって罰則が強化されました。
禁止事項は、自転車運転中のスマホの通話と、運転中に画面を注視することです。罰則内容は以下の通りです。
・「ながらスマホ」:6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・「ながらスマホ」による交通事故:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」は→こちら
●警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」は→こちら
自動車の場合
自動車の「ながらスマホ」は2019年12月の道路交通法改正によってより罰則が厳しくなりました。罰則内容は以下の通りです。
・「ながらスマホ」:6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金/反則金18,000円/違反点数3点
・「ながらスマホ」による交通事故:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金/違反点数6点
「歩きスマホ」「ながらスマホ」による交通事故は実際に多い?
罰則が強化されても、運転中のスマートフォンや携帯電話の使用に起因する交通事故は、依然として深刻な問題となっています。
以下は、警察庁が公開している令和5年(2023年)の統計データです。
・死亡・重傷事故件数:携帯電話等の使用による死亡・重傷事故は122件(全死亡事故に占める割合は1.24%)
・死亡事故率:携帯電話等を使用していた場合、使用していない場合と比較して死亡事故率が約4倍高い
また、ながらスマホによる事故は令和3年以降増加傾向にあり、特に運転中の画面注視や通話が重大な事故につながる危険性があります。
2025年現在は「歩きスマホ」そのものへの罰則はありませんが、実際に事故が起こった場合は誰かを傷つけてしまう上、損害賠償のリスクも発生してしまいします。「歩きスマホ」も「ながらスマホ」もどちらも「一瞬なら大丈夫」という油断が重大事故を招きます。安全のためには、操作が必要な際は必ず安全な場所で停止することが不可欠です。
※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)




