
ほんの数年前まで、日本の日常的な支払いは基本的に現金またはクレジットカードが主役でした。しかし、今やコンビニのレジ、賑やかな飲食店のテーブル、さらには昔ながらの個人商店の店先まで、あらゆる場所にあるのが、QRコード決済です。
驚異的なスピードで普及したQRコード決済ですが、「世界的に見て『進んでいる』のか、それとも日本国内だけで通用する『ガラパゴス』的な進化なのか?」という疑問を抱いている人もいるでしょう。
実際、国内で普段使っているQRコード決済アプリが海外では利用できず、出張や海外旅行の際にはクレジットカードのタッチ決済やApple Payなどに頼りきりになっている方も少なくないのではないでしょうか。詳しく見ていきましょう。
そもそも、なぜ日本でQRコード決済が爆発的に普及したのか?
日本のキャッシュレス化を語る上で最も基本的な指標が、キャッシュレス決済比率です。経済産業省の発表によると、2024年における日本のキャッシュレス決済比率は42.8%に達し、決済額は141.0兆円に上りました(出典:経済産業省)。
2024年の決済額の内訳を見ると、依然としてクレジットカードが82.9%(116.9兆円)と圧倒的なシェアを誇り、キャッシュレスの王座に君臨しています。しかし、少しずつ増えてきているのがQRコード決済です。そのシェアは2024年時点で9.6%(13.5兆円)と、まだ1割に満たないものの、前年からの成長率は著しいです。
対照的に、かつてモバイル決済の主役だった交通系ICカードなどに代表される電子マネーは4.4%(6.2兆円)、デビットカードは3.1%(4.4兆円)に留まっています。

このようにQRコード決済が急速に普及した裏には、国内での官民一体でのキャンペーンが挙げられます。2019年10月の消費税率引き上げと同時に開始された「キャッシュレス・ポイント還元事業」は、最大の推進力となりました。
この事業は、対象店舗でキャッシュレス決済を行うと最大5%のポイントが還元されるというもので、消費者に「キャッシュレスはお得」という強烈なインセンティブを与えました。同時に、これまで導入をためらっていた中小・小規模事業者に対しても、決済端末の導入補助や手数料補助が行われ、加盟店網が一気に拡大するきっかけとなりました。
中小店舗にとって、従来のクレジットカード決済は、専用の決済端末(CAT)の導入コストや比較的高額な決済手数料が障壁となっていました。一方、QRコード決済の多くは、店側が提示したQRコードを客が読み取る「ユーザースキャン方式」であれば、極端な話、QRコードを印刷した紙一枚あれば導入できます。決済手数料も、クレジットカードの3%前後に比べて1%台後半からと低く設定されている場合が多く、これが特に個人経営の飲食店や小売店での導入を促進したのです。
乱立する日本のQRコード決済は「ガラパゴス」?

2025年現在のQRコード決済市場は、まさに「ペイ戦国時代」と言えるでしょう。PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAYといった大手だけでなく、メルペイなど、数多くの事業者が乱立しています。
この状況はよく言えば「健全な事業者間競争が活発である」ものですが、悪く言えば日本の決済市場を内向きにし、国際的な孤立を深める一因となっています。
その要因の1つには、一つのQRコードで複数の決済サービスに対応できる統一規格「JPQR」の普及が進んでいないことが挙げられます。主要プレイヤーの足並みはそろっておらず、限定的な普及に留まっているのが現状です。
この状況は、海外からの旅行者にとってはさらに深刻な障壁となります。自国で使っている決済アプリが日本では使えないケースが多く、日本の複雑な決済環境に戸惑うことになります。
さらに、ソニーが開発した非接触ICカード技術「FeliCa」が2000年代以降に国内で広く浸透したことも、ガラパゴス化の一因です。日本はFeliCaという独自の優れたインフラを国内に張り巡らせてしまったがゆえに、Apple PayやGoogle PayがベースとするNFC(Type A/B)への移行が遅れ、結果として海外の決済サービスとの互換性に乏しい状態が生まれています。
国境を越えた決済統合の遅れ
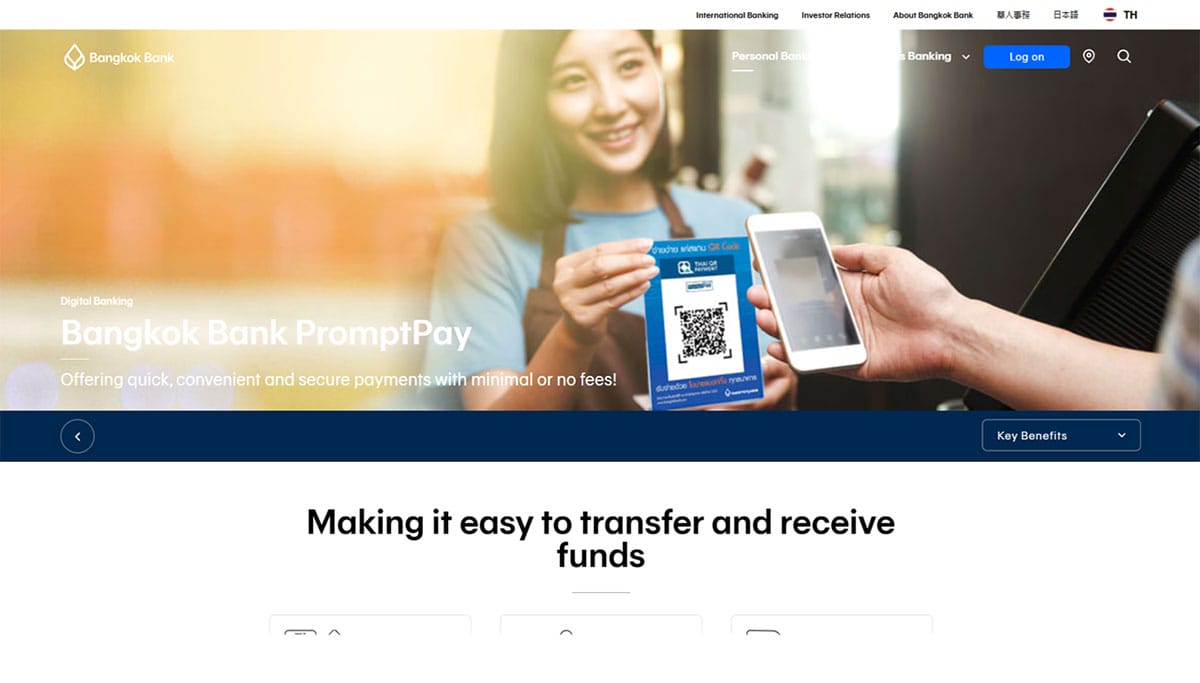
海外の決済サービスとの互換性や、国境を越えた決済統合という観点において、日本より先行している地域には「東南アジア」が挙げられます。インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピンといった東南アジア諸国は、キャッシュレス化において「リープフロッグ(蛙飛び)」現象の典型例にしばしば位置づけられます。
東南アジアにおけるキャッシュレス化は、銀行サービスにアクセスできない人々を金融システムに取り込む「金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)」という社会的な課題解決の側面が強いです。これらの地域では、銀行口座の保有率が低く、クレジットカードインフラも未整備でした。しかし、スマートフォンの急速な普及により、人々は固定的な銀行インフラを飛び越え、一気にモバイルウォレットを利用するようになったのです。
そのため、政府や中央銀行が主導して、安価で即時性の高いリアルタイム送金システム(タイのPromptPay、シンガポールのPayNowなど)を整備し、QRコード決済と連携させる動きが活発です。さらに、ASEAN域内では国境を越えてQRコード決済を相互利用できるようにする連携が進んでおり、地域全体での決済統合という点で日本より先行しています。
「スーパーアプリ」及び「経済圏構築」の遅れ

キャッシュレス化において日本より先行する国には、中国も挙げられます。中国の都市部では80%以上の取引がキャッシュレスで行われ、現金が使えない場面すら珍しくありません。
日本の「〇〇ペイ」は決済が中心的な機能ですが、中国において、決済は「生活プラットフォーム」の一部に過ぎません。その最大の特徴は、決済機能が単独で存在するのではなく、SNS(WeChat)、Eコマース、公共料金の支払い、配車サービス、資産運用、さらには行政サービスまで、あらゆる機能が統合された「スーパーアプリ」の中核として機能している点です。
こうしたスーパーアプリ及び決済機能が中国で受け入れられた背景には、まず東南アジアと同様に「クレジットカードインフラが未整備であったこと」が挙げられます。個人向けの与信システムが存在しない中国ではクレジットカードが中々普及せず、代わりにデビットカードが普及しました。その代表例が「銀聯カード(ぎんれん)/UnionPay」です。
モバイル決済は「クレジットカードが普及しない国」において、デビットカードではない新たな決済手段として爆発的に受け入れられたと言えるでしょう。
さらに政府がデジタル人民元の導入を進めるなど、国家レベルでIT投資やキャッシュレス化を強力に後押ししている点も、民間主導の競争で発展してきた日本とは大きく異なります。日本の「〇〇ペイ」が目指す経済圏の統合レベルは、中国のスーパーアプリには遠く及びません。
日本のキャッシュレスは「始まったばかり」?
冒頭で「2024年における日本のキャッシュレス決済比率は42.8%に達し、決済額は141.0兆円に上った」と述べました。しかし日本のキャッシュレス事情は、皮肉にもリープフロッグ現象を起こした東南アジア諸外国や中国に対して後れを取っているのもやはり事実です。
戦後に急激な経済発展を実現し、キャッシュレス技術が発展するはるか以前から高度な金融インフラや決済インフラを整備してきた日本だからこそ、段階的な技術発展の過程を飛ばして急速に発達する諸外国のキャッシュレス事情に追いつけていない部分が確かにあります。
しかし、良くも悪くも日本のキャッシュレスはまだまだ「始まったばかり」です。そして、日本におけるキャッシュレスは、中国や東南アジアとはまた別の形で発展するべきものでもあるかもしれません。
現金信仰が根強い日本では、中国の都心部のように「決済方法はキャッシュレスのみで、現金が使えないお店」が主流になることは考えづらい面があります。またリープフロッグ現象を起こした諸外国と違い、そもそも日本はキャッシュレス以外の決済インフラも銀行インフラも盤石です。良い意味で「キャッシュレス決済の急速な浸透がなくては、国民が困る」という状況ではありません。
つまり日本のキャッシュレス化の道のりは、海外の成功モデルをただ模倣したものではありません。そして今後も海外の単なる模倣をするべきではないでしょう。
日本のキャッシュレス化は治安の良さや現金への信頼、新しいものへの慎重さといった、自国の複雑な課題や国民性と真摯に向き合い、試行錯誤の末に独自の答えを導き出してきたプロセスそのものであると言えるかもしれません。
その結果として発展した現在の日本のキャッシュレス事情は、中国や東南アジアのあり方と違うという意味では「ガラパゴス」ですが、それはネガティブな意味合いを持つものではないでしょう。
※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)






