
近年、日本の郊外や地方都市で、巨大な建物の建設現場を目にする機会が増えたと感じている人もいるでしょう。その多くは実は「データセンター」。現在、生成AIやクラウドサービスの普及を背景に、まさに建設ラッシュと呼べる状況が続いています。しかし、「資材も高騰しているし、資源の乏しい日本では電気代も高い。これほど多くのデータセンターを建てて、本当に大丈夫なのだろうか?」という疑問を抱く人もいるでしょう。
今回は建設ラッシュが続く「データセンター」に関する問題をご紹介します。
なぜ今、日本でデータセンター建設が相次ぐのか?

データセンターとは、サーバーやネットワーク機器といったIT機器を大量に設置し、24時間365日安定して稼働させるための専門施設です。私たちが日常的に利用するクラウドサービス、動画配信、SNS、そして近年急速に普及した生成AIなど、あらゆるデジタルサービスは、この「見えないインフラ」によって支えられています。特に、膨大な計算能力を必要とする生成AIの登場は、データセンター需要を爆発的に押し上げる最大の要因となりました。
日本のデータセンター市場は、国内企業だけでなく、海外の投資家からも大きな注目を集めています。その理由は、日本の持つ「安定性」にあります。不動産サービス大手JLLの分析によれば、アジア太平洋地域における主要なデータセンターハブ(東京、香港、シンガポール、シドニー)の中でも、安定したインフラ、電力供給、そして高度なセキュリティを誇る日本の人気が高まっています。
特に、データの保管場所に関する法規制(データ主権)の重要性が増す中で、安全な「避難港」と見なされる日本は、投資先として非常に魅力的です。
実際に、フランスの大手保険会社AXAグループが東京のデータセンターに約220億円を投資した事例や、米Equinixとシンガポール政府投資公社(GIC)が合弁で東京・大阪にデータセンターを建設する計画など、海外からの大規模投資が相次いでいます。
市場規模は拡大の一途
近年はデータセンターに限らず、一般的な建築でも資材高騰が問題視されています。建設コストの高騰という逆風にもかかわらず、日本のデータセンター市場は力強い成長を続けています。総務省の「令和6年版 情報通信白書」によると、国内のデータセンターサービスの売上高は、2022年の約2.1兆円から、2027年には約4.2兆円へと倍増すると予測されています。
AIが“電気を食う”時代:日本の電力は足りるのか?
ここで冒頭の疑問に立ち戻りましょう。資材も高騰しているし、資源の乏しい日本では電気代も安くはありません。それでもこれほど多くのデータセンターを建設して、本当に大丈夫なのでしょうか。データセンターの建築ラッシュで懸念されるのは、まずは電力です。
大規模なデータセンター1つで、人口100万人規模の都市に匹敵する電力を消費するとの試算もあり、電力供給への懸念が高まっています。米国の一部地域では、データセンター需要が原因で家庭の電気料金が最大60%上昇する可能性も報じられており、日本でも同様のリスクが考えられます。
データセンターを1つ建設するごとに100万人規模の都市に匹敵する電力を消費するならば、そのデータセンターを増設するたびに「100万人規模分の電力」がさらに必要になることも意味します。電力不足の懸念が生まれるのは周辺住民にとっては当然のことでしょうし、電力が「不足」しなくとも「当該地域の電気代が上がる」リスクも考えられます。
CO2排出について
大量の電力消費は、二酸化炭素(CO2)排出による地球温暖化という環境問題に直結します。経済産業省が令和4年に発表した「令和3年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業」によると、データセンターのエネルギー消費の内訳は、サーバーなどのIT機器が半分、そして残りの多くを機器を冷やすための空調設備が占めています。
このエネルギー効率を示す指標として「PUE(Power Usage Effectiveness)」が用いられます。PUEは、データセンター全体の消費電力をIT機器の消費電力で割った値で、1.0に近いほど効率が良いとされます。
日本政府は省エネ法に基づき、データセンター事業者にPUEの目標値を「1.4」と設定し、省エネ努力を促しています。しかし、AIサーバーのように発熱量が大きい機器が増える中で、この目標を達成し、環境負荷を低減していくことは簡単ではありません。
カギを握る「冷却技術」と「再生可能エネルギー」
先にも述べた通り、データセンターの電力消費の大半を占めるのは「機器の冷却」です。つまり周辺地域に悪影響を及ぼすことなく、データセンターを持続的に運営するには冷却技術の革新は欠かせません。

そこで注目されているのが、「液浸冷却」です。
従来、機器の冷却は良くも悪くも地道な「空冷方式」で行われています。いわば単に扇風機で熱気を追い出すようなものだと言えるでしょう。
これに代わり、サーバーを特殊な液体に直接浸して冷却する「液浸冷却」技術が注目されています。この技術は、冷却効率を飛躍的に高め、消費電力を約40%削減できると期待されています。
再生可能エネルギーと「デジタル田園都市」
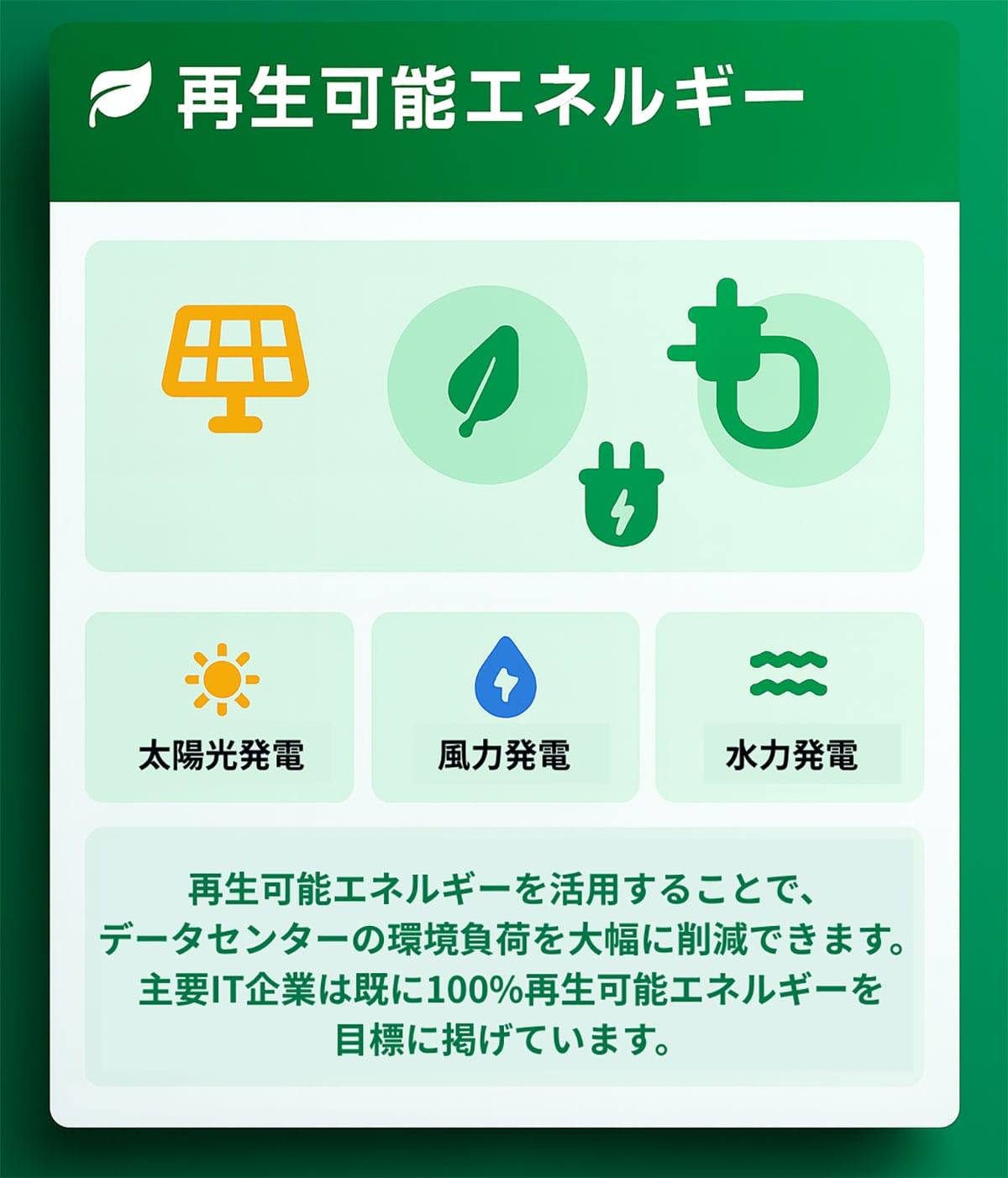
総務省の「令和6年版 情報通信白書」によると、現在、日本のデータセンターの約6割が東京圏に集中しており、大阪圏を含めると8割を超えます。この一極集中は、首都直下地震などの大規模災害が発生した際に、日本全体の通信インフラが麻痺するリスクをはらんでいます。
この課題に対応するため、政府は「デジタル田園都市国家構想」を掲げ、データセンターの地方分散を推進しています。具体的には、再生可能エネルギーが豊富な北海道や九州などを新たな拠点とする構想です。
こうした再生可能エネルギーを用いたデータセンター運営は、電力の確保に加え、環境負荷低減の面でも国内外で注目が高まっているものです。たとえば海外ではGoogleが地熱発電直結のデータセンターを運営している事例もあります。
日本国内でも、北海道美唄市で雪を使った冷却システムを導入し、CO2排出ゼロを実現した「ホワイトデータセンター」のような特徴的な取り組みが生まれています。こうした取り組みは、環境負荷を低減するだけでなく、企業のブランド価値向上やその地域の価値向上にも繋がります。
「データセンターをこれ以上建てて大丈夫なのか?」という問いに対する答えは、単純な「はい」か「いいえ」ではありません。AIやクラウドが社会の隅々まで浸透する中で、データセンターの増設は、もはや避けては通れない道です。問題は、その「建て方」と「使い方」にあります。
建設コストや人手不足、そして深刻な電力消費の課題に正面から取り組まなければ、デジタル社会の成長は持続不可能です。政府が推進する地方分散によるリスク低減、そして企業が進める省エネ技術の開発や再生可能エネルギーの導入は、そのための重要な一歩だと言えるでしょう。
※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)




