
2000年代初頭の日本の携帯電話市場では、NTTドコモ、au、そしてJ-PHONE(後のボーダフォン、現ソフトバンク)の3大キャリアが激しい覇権争いを繰り広げていました。その中で、独自の存在感を放っていた第4のキャリアが『ツーカー』です。
当時のCMにはお笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが出演。カメラにどアップで映り、「なんかもう必死でしょ、最近の携帯。話せりゃええやんって思いますけどね」と話すという印象的な映像を覚えている人も少なくないのではないでしょうか。
そのCMが表しているとおり、派手な機能競争とは一線を画し、「シンプル」と「低価格」を武器に、堅実なユーザー層から支持を集めていました。しかし、そのツーカーは2008年、静かに市場から姿を消しました。

ツーカーの携帯電話は、今日の携帯電話市場で典型的に見られる「ハイエンド」「高価格」とは別物です。これを「低価格帯で提供されるガラケー」ととらえると、ツーカーの携帯電話は2025年現在の視点で見ても、一定のニッチ需要に応え得るものだと言えるのではないでしょうか。
ではツーカーの携帯電話はなぜ消えたのでしょうか?具体的に見ていきましょう。
ツーカーの歴史
ツーカーの歴史は、1985年の通信自由化に端を発します。通信自由化以後は、携帯電話市場への新規参入が活発化し、ツーカーは1992年頃からその姿を現し始めました。母体となったのは、意外にも自動車メーカーの日産自動車です。
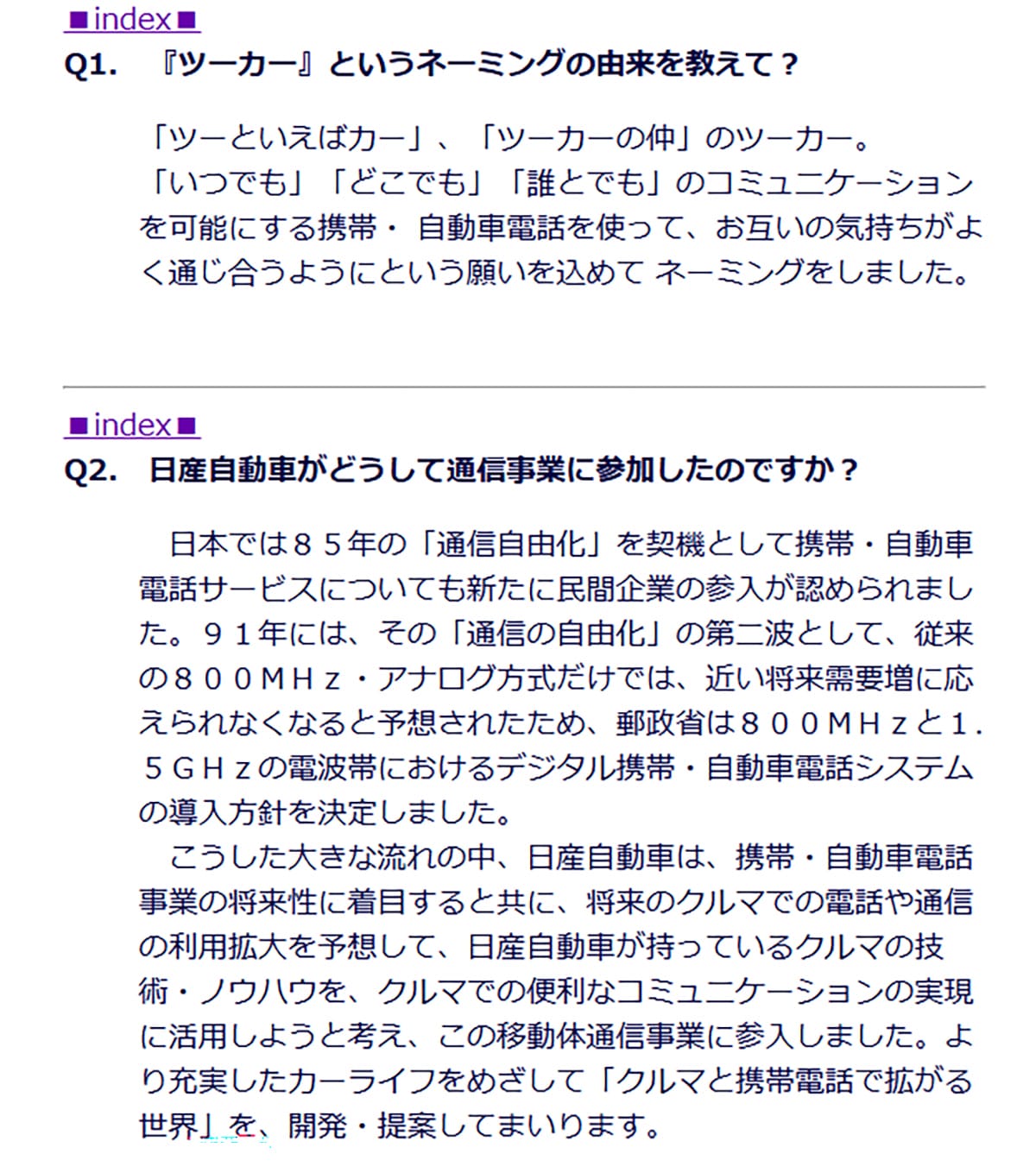
そして1990年代半ばの携帯電話市場は、NTTドコモ、IDO・DDIセルラー連合(後のau)に加え、第三の勢力としてJ-PHONEやツーカーが加わり、しのぎを削る構図となった。
明確なニッチ戦略を選んだツーカー

90年代~00年代の日本の携帯電話市場は、世界的に見ても極めて稀なレベルで発展を遂げていました。多くのキャリア及びメーカーは多機能化や世界初の新機能の搭載へと、積極的に乗り出していた時期だと言えるでしょう。
しかしツーカーは、その流れに逆行するかのように、明確なニッチ戦略を打ち出します。「最新機能は不要、シンプルに通話ができれば良い」と考えるユーザー層に照準を合わせ、分かりやすく低価格な料金プランで差別化を図ったのです。
たとえば1998年には、業界に先駆けてプリペイド式携帯電話「プリケー」を発売しました。さらに、2003年に導入した2年間の継続契約を条件に基本料金を大幅に割り引く「ツーカーV3」といったプランは、現在の携帯料金プランの原型ともいえる画期的なプランだったと言えるでしょう。
「3Gへ移行しない」ツーカーの決断
ツーカーの歴史を理解する上で欠かせないのが、2Gから3Gへの技術的な大転換です。ツーカーが採用していた通信方式は第2世代(2G)のデジタル通信規格でした。
そこへ登場したのが「3G(第3世代移動通信システム)」。3Gは、国際電気通信連合(ITU)によって標準化が進められ、「世界中で同じ端末が使えること」を目指した国際規格でした。技術的には、W-CDMAやcdma2000といった方式が採用され、2Gとは比較にならないほどの高速・大容量通信を実現しました。この技術革新は、携帯電話を単なる「通話の道具」から、インターネット接続、音楽配信(着うた®)、動画視聴といった「データ通信を楽しむ端末」へと変貌させる、まさに技術的な転換点でした。
2000年代に入ると主要キャリアは3Gの展開を強化。たとえばNTTドコモは2001年、世界に先駆けて3Gサービス「FOMA」を開始し、技術力を世界にアピールしました。
一方でツーカーは「3Gへ移行しない」という決断を行います。その最大の要因としては当時総務省が1999年に同一地域での免許人数を「最大3」とする方針を正式決定し、これによって既存大手3グループ(NTTドコモ、KDDI、J-PHONE)が優位となる構造ができあがってしまいました。つまり、ツーカーが新たにライセンスを獲得することは現実的ではありませんでした。
3Gへの移行を見送ったことは、最新技術を搭載した端末開発の競争から脱落することを意味しました。
その後、他社がカメラ機能やデザイン性を競い合う中、ツーカーが提供できるのは旧世代の技術に基づいたシンプルな端末のみ。消費者の心を掴む「キラー端末」を生み出すことができず、端末ラインナップの魅力は次第に薄れていきました。
そして2005年にKDDIは、完全子会社となっていたツーカーグループ3社(ツーカーセルラー東京、同東海、ツーカーホン関西)を吸収合併することを発表。その後、2006年6月30日にはツーカーの新規加入受付が終了し、サービスは2008年3月31日をもって完全に終了しました。(※なおサービス終了後、ツーカーが使用していた貴重な1.5GHz帯の周波数は、逼迫していたauの3Gサービスの帯域補強などに転用されました)
ツーカーが目指した「ニッチ戦略」は間違っていたのか?
ツーカーが設立当初から「シンプル・低価格」という明確な戦略で、大手キャリアとは異なる価値を提供し、多くのユーザーから支持を得たことは紛れもない事実です。しかし、3Gという次世代技術に移行できなかったことでその戦略は道半ばで終わったと言えます。
とはいえ「ニッチ戦略」でシニア層らを狙う試みそのものには2025年現在の視点で見ても、光る部分が多々あります。

その象徴的な端末が、2004年に発売された「ツーカーS」です。ツーカーSはディスプレイがなく、メール機能、ブラウザもないというシンプルを追求した端末。見た目はまるで固定電話の子機でしたが、ツーカーはこれを「黒電話並みの使いやすさで説明書不要の携帯電話」として当時のシニア向けに売り出し、同年度のグッドデザイン賞ユニバーサルデザイン賞を受賞するなど、大きな反響を集めました。
こうした「低価格」×「シンプルな端末」の組み合わせは、2025年現在の視点で見ても色褪せてはいません。
たとえばMMD研究所の調査によると、MVNO(格安SIM)のシェアは約9.1%を占めており、低価格プランのニーズが一定数あるのは確かです。
特にシニア層の支持を集める「イオンモバイル」や、超低価格プランで存在感を示す「日本通信SIM」の成功は、ツーカーが目指した方向性を、2025年現在において体現しているものだと言えるのではないでしょうか。
中でもイオンモバイルは全国のイオン店舗での手厚いサポートを強みに、デジタルに不慣れなシニア層の獲得に成功しています。もしツーカーが存続し、「超低価格」「シンプル機能」というブランドイメージをさらに先鋭化させつつも同様の店舗サポート戦略を展開できていれば、今日の格安SIM市場で有力なプレイヤーの一角を占めていた可能性は十分に考えられるでしょう。
ツーカーの挑戦は、時代を先取りしすぎていたのかもしれません。しかし、そのDNAは、形を変えて現代の格安SIM事業者に受け継がれていると言えます。
※サムネイル画像(Image:「ツーカーセルラー東京(Wayback Machine:2004年6月)」より引用)




