
かつては日本の携帯電話に「当たり前」の機能だったFeliCa。しかし、QRコード決済やクレジットカードのタッチ決済など、キャッシュレス手段が爆発的に増えた今、海外メーカー製のスマホを中心に魅力的なスペックやデザインでありながら、FeliCa非搭載のモデルが市場で目立つようになっています。
「FeliCaやおサイフケータイは、もう古い技術(オワコン)なの?」
という声も聞こえてきます。この記事では、なぜFeliCaを搭載しないスマートフォンが増えているのか、その背景を見ていきましょう。
日本のキャッシュレス決済を支えてきた「FeliCa」
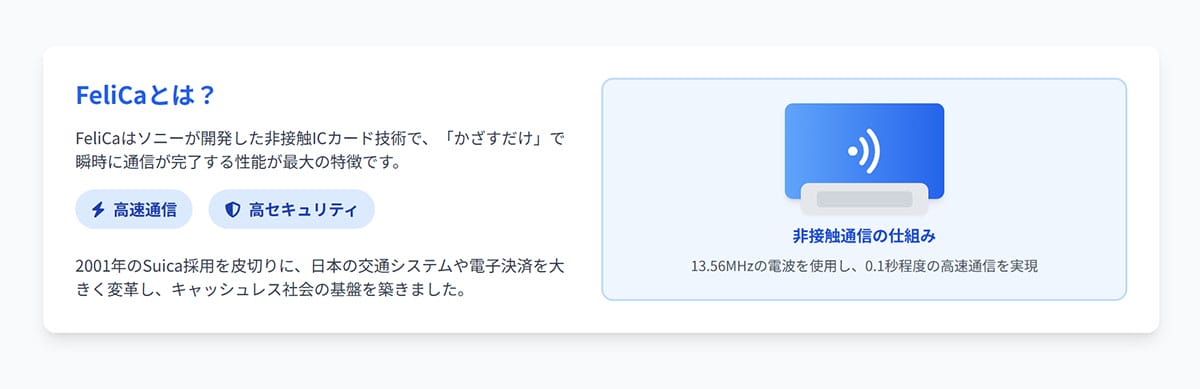
FeliCaはソニーが開発した非接触ICカード技術。「かざすだけ」で瞬時に決済などの通信が完了する性能が最大の特徴です。

その歴史は、2001年にJR東日本のIC乗車券「Suica」へ採用されたことから本格的に始まります。これを皮切りに、全国の交通系ICカードや、「Edy」(現在の楽天Edy)などのプリペイド型電子マネーへと、FeliCaの採用が次々と拡大しました。さらに2004年には携帯電話にFeliCaチップが搭載され、「おサイフケータイ」としてモバイル決済の扉を開きました。

おサイフケータイの最大の魅力は、複数の電子マネーやクレジットカード情報をスマートフォン一台に集約できる点です。Suica、PASMOなどの交通系ICカード、楽天Edy、iD、QUICPayなどの主要な電子マネーはもちろん、クレジットカード決済もおサイフケータイ経由で行うことが可能です。
たとえば「総務省 平成27年版情報通信白書」でも、FeliCa開発以降、「非接触ICカード型の電子マネーの利用が広がった」と記されています。
FeliCa非搭載スマホが増加する2つの大きな理由
FeliCa非搭載スマホが増加している理由は、端末をFeliCaに適合させるためにコストがかかることと、非接触決済の世界標準がFeliCaではないことが挙げられます。
端末開発を遅らせる足かせとしてのFeliCa
スマートフォンメーカーが自社製品にFeliCa(おサイフケータイ)を搭載するためには、単に対応チップを組み込むだけではありません。そこにはライセンスの処理や日本独自の仕様に適合させるための開発・検証コストという、目に見えにくい費用が発生します。
特にグローバル市場で数百万、数千万台単位で製品を展開するメーカーにとって、この「日本市場限定」の追加コストは無視できないでしょう。詳しくは後述しますが、現在、世界の多くの国では、国際標準規格である「NFC Type A/B」の搭載が一般的です。日本市場のためだけにFeliCa対応のハードウェア設計変更やソフトウェアの最適化を行うことは、グローバルで共通化された設計・生産ラインを持つメーカーにとって、コスト増とサプライチェーンの複雑化に直結します。

こうした背景から、OPPOやシャオミといったメーカーは、あえてFeliCaを搭載しないモデルも日本市場に投入するという戦略を採り始めています。彼らは、FeliCa非搭載でも、その分コストを抑え、グローバルと同時に最新モデルを投入できるスピード感を武器にすれば、日本の消費者にも受け入れられると判断しているのです。FeliCa対応は、もはや日本市場での成功に不可欠な要素ではなく、メーカーのグローバル戦略を縛る「足かせ」となりつつあるのかもしれません。
「NFC Type A/B」が世界標準という現実
先述した通り、非接触決済の世界標準がFeliCaではない、という厳然たる事実は大きな要因です。
日本では交通系ICカードを中心にFeliCaがデファクトスタンダード(事実上の標準)となりましたが、世界的にはVisaのタッチ決済やMastercardコンタクトレスに代表される「NFC Type A/B」という規格が非接触決済の標準となっています。海外では、このNFCに対応したクレジットカードやデビットカードをそのまま公共交通機関の改札にかざして乗車できる「オープンループ」と呼ばれる仕組みがロンドンやシンガポール、ニューヨークなど多くの都市で普及しています。
日本国内でもNFC Type A/Bは広がりを見せており、訪日外国人観光客の増加などに伴い、店舗側でも国際標準のNFC Type A/B(いわゆる「タッチ決済」)に対応した決済端末の導入が急速に進みました。日本の決済シーンがFeliCa一強から、多様な規格が共存する時代へと移行しているため「FeliCaを省略する」のは決済シーンにおいても、端末開発の面においても現実的な選択肢になりつつあるのです。
FeliCa規格は本当にオワコン?強みと新たな挑戦について
「FeliCaはオワコン」という評価は、やや短絡的で実態を正確に捉えていないと言えるでしょう。FeliCaは日本の交通システムや決済シーンにおいて、依然として重要な役割を担っており、その高速性と信頼性は他の技術では代替が難しい独自の価値を持ち続けています。毎日何百万人もの人々が利用する首都圏の交通インフラを、遅延なくスムーズに処理し続ける能力は、NFC Type A/B規格が容易に追随できるものではありません。この「社会インフラとしての安定性」は、FeliCaの揺るぎない中核価値です。
またソニーには「FeliCa技術を単なる決済や交通の手段として終わらせるつもり」はないと見られます。その一例が、商業施設向けの屋内行動分析プラットフォーム「NaviCX(ナビックス)」です。これは、従業員や顧客が持つFeliCa搭載デバイスから位置情報や動線データを収集・分析し、店舗運営の効率化や顧客体験の向上につなげるBtoBソリューションです。実際、ホームセンター大手のカインズが実証実験を行うなど、具体的な活用も始まっています。
もしかしたらさらに「NFC Type A/B」が国内で浸透し、FeliCa非対応スマホが増加した場合、おサイフケータイは「オワコン」になるのかもしれません。決済はクレジットカードのタッチ決済やQRコードがメインの人にとって、FeliCaはあまり意味がない技術かもしれません。
しかし、Felicaはそれでもなお強力な通信技術であり、BtoBの現場などで長くソリューションとして生き続けるでしょう。
※サムネイル画像は(Image:「Google Play」より引用)




