かつては「あって当たり前」の存在だった駅やカフェ、公共施設のフリーWi-Fi。しかし今、「気づいたらなくなっていた」と感じることはありませんか?
「ギガが足りない」ときの駆け込み寺的存在として、また訪日外国人観光客にとっての生命線として重宝されてきた公衆無線LAN(フリーWi-Fi)に、一体何が起きているのでしょうか。

自治体にも広がる「フリーWi-Fi離れ」の波
各地の自治体が提供しているフリーWi-Fiはサービスの提供終了が相次いでいます。
たとえば静岡県森町は、2019年から公共施設や避難所などで提供してきた公衆無線LAN「Morimachi_Free_Wi-Fi」を、2025年12月(一部は2026年6月)をもって終了すると発表しました。

その理由として静岡県森町は、日常的な利用頻度の低さや機器更新コストの高さなど、複数の要因を挙げています。
民間で進む「フリーWi-Fi離れ」

フリーWi-Fiのサービス終了は数年前から、主に民間で大きな潮流となっていました。東京メトロでは2022年6月に車両内の「Metro_Free_Wi-Fi」の提供を終了、都営バスや東武鉄道、小田急電鉄といった公共交通機関でも同様にサービスを終了しました。
さらに、セブン&アイ・ホールディングスの「7SPOT」やファミリーマートの「Famima_Wi-Fi」といったコンビニ大手のサービスも相次いで終了しており、私たちの生活からフリーWi-Fiの選択肢が着実に減少しているのが現状です。
では、なぜこれほどまでにフリーWi-Fiは「オワコン」扱いされるようになってしまったのでしょうか。
なぜフリーWi-Fiは姿を消しつつあるのか
町中からフリーWi-Fiが消えつつある原因はいくつか挙げられますが、主に、東京五輪におけるインフラ整備の役割を終えたこと、個人のスマホキャリアで「データ無制限」が広がったこと、フリーWi-Fiそのものの危険性が認識されはじめたことなどが可能性として考えられます。
東京五輪におけるインフラ整備の役割を終えた
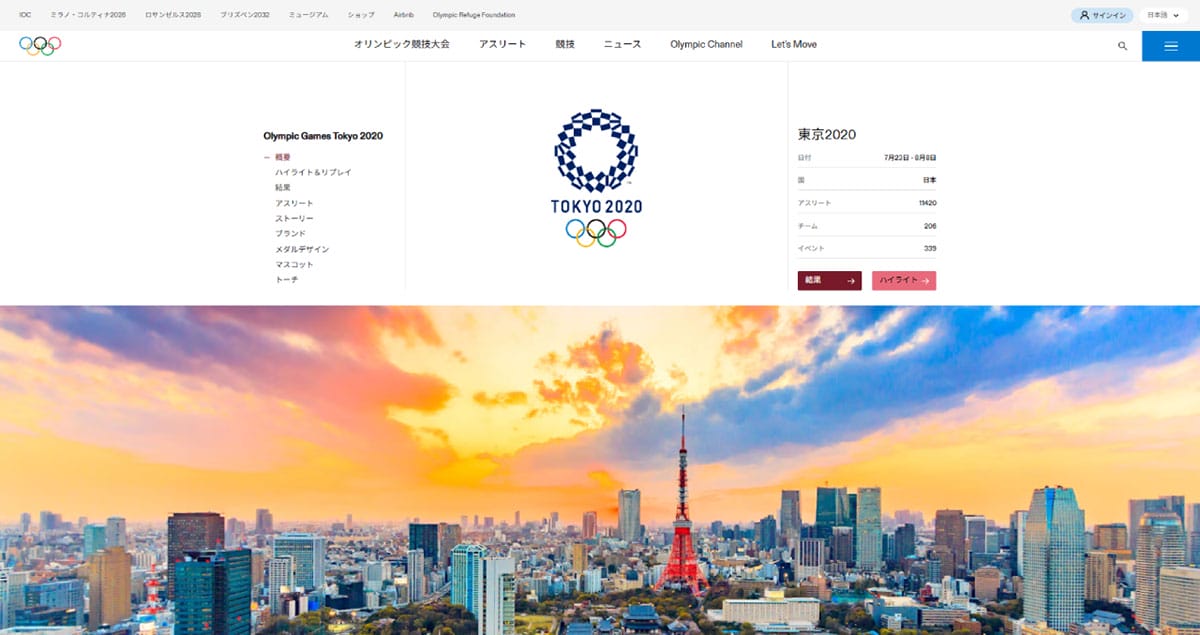
多くのフリーWi-Fi、特に公共交通機関で整備されたものは、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、急増する訪日外国人観光客向けの通信インフラとして整備された側面が非常に大きなものでした。実際、全国のWi-Fiスポット数は、誘致が決まった後の2015年4月の約4万カ所から、2018年12月までに約14万カ所へと飛躍的に増加しました。
しかし、ご存知の通り、東京五輪は新型コロナウイルスの影響で1年延期された上、異例の無観客開催となりました。誘致時に期待されていたインバウンド需要は幻となり、フリーWi-Fiは本来の目的を十分に果たせないまま、終了のタイミングを迎えることになりました。結果として、多くの事業者が五輪後のタイミングでサービス提供事業者との契約を更新せず、サービス終了という判断を下すことになりました。
「データ無制限」の広がり

携帯キャリア各社が提供する料金プランも、かつての「ギガを節約する」時代から、「データ無制限」が当たり前の時代へとシフトしました。特に通信インフラが整備された都市部では、多くのユーザーが自身のスマートフォン回線で快適なデータ通信を行えるようになりました。
わざわざ手間をかけてフリーWi-Fiを探し、接続設定を行い、時には不安定な通信に悩まされる、といった必要性は薄れてきました。多くの人にとって、フリーWi-Fiは「あれば使うかもしれないが、なくても困らない」存在へと変化したと言えるでしょう。
フリーWi-Fiそのものの危険性が顕在化している
利便性の裏側で、フリーWi-Fiには常にセキュリティのリスクが付きまといます。特に問題となるのが、悪意のある第三者が設置した「なりすましアクセスポイント」の存在です。正規のWi-Fiとそっくりのネットワーク名(SSID)で利用者を誘い込み、一度接続してしまうと、通信内容が盗聴され、入力したIDやパスワード、クレジットカード情報といった個人情報がすべて抜き取られてしまう危険性があります。
また、そもそも通信が暗号化されていないフリーWi-Fiも多く、専門的な知識があれば比較的容易に通信内容を傍受できてしまうリスクがあります。近年、さらに、その手口はますます巧妙化しており、利用者が一見して危険性を判断するのは困難です。こうした根強いセキュリティへの懸念が、利用者離れの一因となっていることも否定できません。
今後のフリーWi-Fiに期待される役割とは
一方、フリーWi-Fiが完全に不必要になったわけではありません。今後は、災害時の通信インフラ、社会的インフラとしての役割が期待されるでしょう。
災害時の通信インフラ

地震や台風といった大規模災害が発生し、携帯電話の基地局がダメージを受けて広範囲な通信障害が起きた際、フリーWi-Fiは「命綱」となり得ます。災害時に誰もが無料で利用できるよう開放される統一ネットワーク「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」は、その代表例です。このネットワークを通じて、人々は安否確認の連絡を取ったり、災害情報を収集したりすることができます。
森町ではサービス終了の理由として、日常的な使用頻度の低さや機器更新の高額さを公表していますが、状況によっては、被災者の情報収集や連絡手段を確保する重要な手段として、社会インフラとしての重要性は依然として高いと言えるでしょう。
「量」ではなく「質」への転換
「フリーWi-Fiはオワコンになった」と断じるのは早計ですが、その役割が大きな転換期を迎えていることは間違いありません。
かつてのような「誰もが日常的に、どこでも無料で使う」ためのインフラとしての役目は、モバイル通信網の充実に伴い、終わりを迎えつつあります。その一方で、「災害時」「訪日外国人観光客向け」「大規模イベントや通信過疎地域での特定ニーズへの対応」といった、いわば「社会インフラ」としての重要性はむしろ高まっています。
もし、このまま採算が合わないという理由だけでフリーWi-Fiが町から完全に消えてしまったら、私たちは災害という非常事態における重要な通信手段の一つを失うことになります。また、日本を訪れる多くの観光客が不便を強いられ、データ容量の少ないプランを契約している国内の通信弱者との情報格差が広がるリスクも考えられます。
今後のフリーWi-Fiに求められるのは、むやみに設置数を増やす「量」の拡大ではなく、本当に必要な場所に、安全で高品質な通信を提供する「質」への転換です。そして利用者もまた、フリーWi-Fiが必ずしも安全・無償ではないことを理解し、その必要性やセキュリティリスクを天秤にかけながら、賢く活用していく姿勢が求められていると言えるでしょう。
※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)





