NetflixやU-NEXTなどの動画サブスクリプションサービスを利用し、スマホやPCで映像作品やスポーツ中継を楽しむのは「ごく当たり前」のこととなりました。会員の視聴行動を分析したコンテンツラインナップの検討や脚本の制作なども一般的なことになりつつあります。
もっともこうした「データ活用」は決して新しいアイデアではなく、たとえば日本では『TSUTAYA』を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)社による、Tポイント(現:Vポイント)を活用した高度なマーケティングは早くから実現されています。

そんな『TSUTAYA』運営企業が1990年代末に行った壮大なチャレンジが、衛星放送『ディレクTV』です。
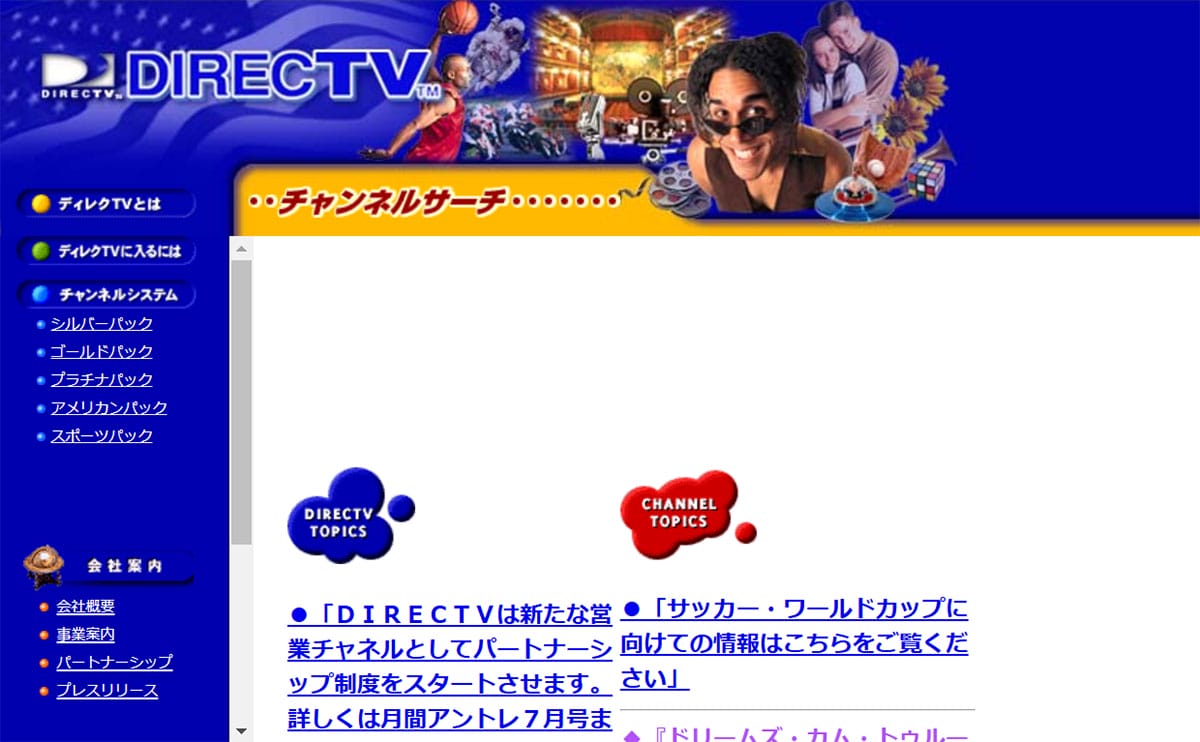
そもそも「ディレクTV」とは、アメリカの衛星放送サービス。90年代にTSUTAYAの運営企業がアメリカの衛星放送サービスを日本に持ち込むようにして、放送事業に参戦した形になります。
当時のTSUTAYAは880店、会員数900万人(1995年当時)で日本トップのビデオ・CDチェーンという状況。つまり、どんな属性の人がどの店で、どのビデオやCDを借りたのかという情報をリアルタイムで処理する体制をすでに確立していました。
また、衛星放送事業参入により、パソコンによる衛星放送受信や映像へのオンデマンドデータ付加に乗り出すとも見込まれていました。
実際、1997年に行われた基調講演では、衛星放送を視聴しながらその内容を検索できるという「ディレクPC」という新サービスの概要も紹介されていました。
つまり、今日のビッグデータ×映像サービスの掛け合わせを90年代に実現しようとした試みだったとも言えるでしょう。しかし、実際にはディレクTVは1997年末に参入し、2000年に撤退が決まります。
なぜ『ディレクTV』は日本では失敗したのでしょうか? 詳しく見ていきましょう。
『スカイパーフェクTV!』の誕生と市場からの出遅れ
ディレクTVの日本法人がサービスを開始した90年代後半は、日本の衛星放送の黎明期にあたります。ディレクTVは1997年末に放送を開始しています。
この「97年末の放送開始」は衛星放送の黎明期に競合他社に差をつけるには、一手遅かったタイミングだったかもしれません。たとえばスカパーの前身にあたる「パーフェクTV!」は1996年に放送開始済み。つまりディレクTVは1年以上、後発です。
そして1998年にはパーフェクTVとJスカイBが合併し、『スカイパーフェクTV!』が誕生。この合併により、『スカイパーフェクTV!』は圧倒的な規模で市場を席巻し、ディレクTVはますます市場の最先端から出遅れた形となりました。

たとえば総務省が公開している1999年のデータによると、スカパーに対してディレクTVはチャンネル数、委託放送事業者数、会員数のすべてで極めて大きな差があります。会員数で5倍近い差がありあり、1999年初頭時点でディレクTVの「敗戦」は明らかなものになっていたと言えます。
F1放映権獲得の失敗
ディレクTVが国内で会員数を伸ばすチャンスは、日本側が主導する形でヒューズ社に提案していた『F1放映権』の獲得しか無かったと言えるでしょう。
冒頭でも述べた通り、ディレクTVは米衛星放送を日本に輸入する形でスタートした衛星放送でした。また、ディレクTVは、ヒューズ・エレクトロニクス社の傘下にある独立会社でした。そしてディレクTVの日本展開に当たっては、株式の持ち分はCCC社が35%、ヒューズ社が35%となりました。
そしてディレクTVはCCC社の創業者である増田宗昭氏が戦略として掲げた『F1放映権獲得』を巡って、持ち分が同じCCC社とヒューズ社が対立する形となり、最終的に放映権獲得は頓挫することとなります。
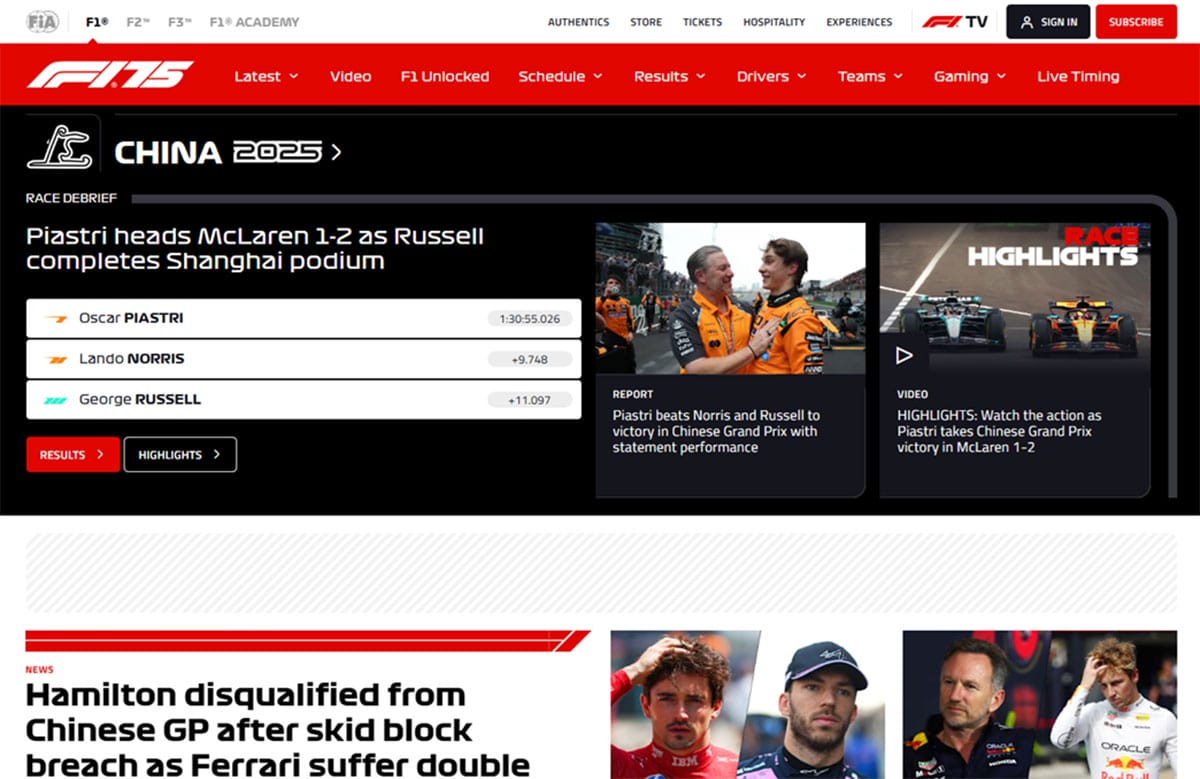
なお増田氏はディレクTVについて振り返った自著『情報楽園会社』で「インディ500は知っていてもF1の魅力を知っている人はほとんどいなかった」と、F1を日本で放映したいと主張してもヒューズ社の賛同を得られず、事業がうまく進まず、挫折を味わったと振り返っています。
資金力と「タイムリミット」
ディレクTVの撤退には資金力の問題も影響しました。増田宗昭氏は2005年4月に公開された糸井重里氏主宰のウェブサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』での糸井氏との対談で、当時のCCC社の経常利益が40億~50億円だったとしたうえで、その4年分にあたる200億円をディレクTVに出せるリミットに設定したと明かしています。
ここから分かるのは、ディレクTVが「CCC社の4年分」というあらかじめ定められたタイムリミットのもとでスタートしたサービスだったということです。出資の過半数を握っていない企業が、他の出資者の理解を得ながら新たなビジネスに挑戦するには、「4年間」という期限はあまりにも短すぎたのではないでしょうか。
仮にタイムリミットが倍の8年であれば、事情は変わっていたかもしれません。たとえば競合の『SKY PerfecTV!(スカパー!)』は、2002年日韓W杯をきっかけに、極めて大きく知名度を向上させました。このように、ディレクTVも00年代以降の衛星放送の波をどこかのタイミングで掴んでいたかもしれません。
TSUTAYAの店舗や会員基盤との相乗効果が出る「前夜」の撤退
「資金力」の不足があまりにも早い撤退につながったのは、00年代以降のTSUTAYAの強固なマーケティング基盤に「衛星放送」が加わらなかったという点で、衛星放送の歴史からみても勿体ない点の1つです。
ディレクTVは1997年末に参入し、2000年にサービスが終了しました。実際に国内である程度の「熱」があった期間はわずか2年程度だったと言えるでしょう。

この期間はあまりに短く、TSUTAYAが90年代当時に実現していた強固な会員基盤と分析力を活かす前に撤退が決まってしまった印象も否めません。TSUTAYAは00年代以降、Tポイント事業でビッグデータ基盤を築き上げ、レンタル事業に加えてポイント事業で一時代を築きます。しかしそのマーケティング対象に『ディレクTV』が入っていないのは残念なことです。
ディレクTVは映像へのオンデマンドデータ付与にも積極的であり、一方向的な視聴ではなく双方向的な視聴スタイルに積極的なサービスでもありました。
もしかしたら各会員の「視聴データ」と「TSUTAYAのレンタルデータ」「Tポイント経済圏の購入データ」を突合するビッグデータ分析が00年代に実現した可能性も十分にあります。たとえば「衛星放送でどのジャンルの番組を見たユーザーが、何日後にどの商品を購入する可能性が高いのか」といった分析基盤が確立したかもしれません。

冒頭でも述べた、こうしたビッグデータ×映像サービスの掛け合わせは今日では非常に高いレベルでNetflixが実現しています。しかし今日のNetflixが見ているのと同じ景色をディレクTVはすでに90年代に見ていたのかもしれません。
2007年にDVD宅配レンタルだったNetflixが「動画配信を始めた」ように、90年代にCCC社は「衛星放送を始めた」と言えます。ディレクTVは20年時代を先取りしたサービスだったものの、その時代の先取りが実る前に事業が終焉してしまったと言えるでしょう。
※サムネイル画像は(Image:「ディレクTV公式サイト(1998年:Wayback Machine)」より引用)




